ヨーロッパで日本の川を考える -国際学会で乙川に関する研究成果を発表してきました!
五三さんは、東京大学の学生だった2022年に「五三くんの研究だったら乙川の話を聞くべき!」と共通の知人に紹介され乙川に足を運びました。以来、現在は九州大学に勤務しながら、変わらず乙川をフィールドに「人と川の心のつながり」をテーマとして研究を続けている研究者です。
この夏には、フランス・リヨンと東京で開催された国際会議で乙川の事例を発表してくださいました。かねてより「乙川は世界的に見ても最先端の取り組みをしている」と熱く語っていた五三さん。その乙川が世界の研究者たちの目にどう映り、どのような評価を受けたのか。ぜひ五三さんのレポートをご覧ください。(山田)
*****
こんにちは!ONE RIVER流域研究員の五三と申します。私は、2022年から乙川をフィールドに、人と川との心の結びつきについて研究を進めてきました。現在は、九州大学を拠点に、研究活動をしております。
この7月には、これまでの研究成果を海外の研究者に発表し、多くのポジティブなリアクションをいただくことができました。みなさまの多大なご協力あってのことと心より感謝申し上げます。今回の記事では、立て続けにおこなわれた2回の発表の様子と、そこで得られた私の知見をご紹介したいと思います。
まず初めは、フランスはリヨンで開催されたI.S.Riversという国際会議です。I.S.Riversは、川に関わる世界中の研究者・実践者が分野の垣根を超えて集まる大変ユニークなイベントであり、2018年に第1回が実施され今回が第3回という比較的新しい取り組みでもあります。今回は、Rivers and society(川と社会)という新テーマが設定され、なんとそのテーマの特集に乙川の写真が使われていました!
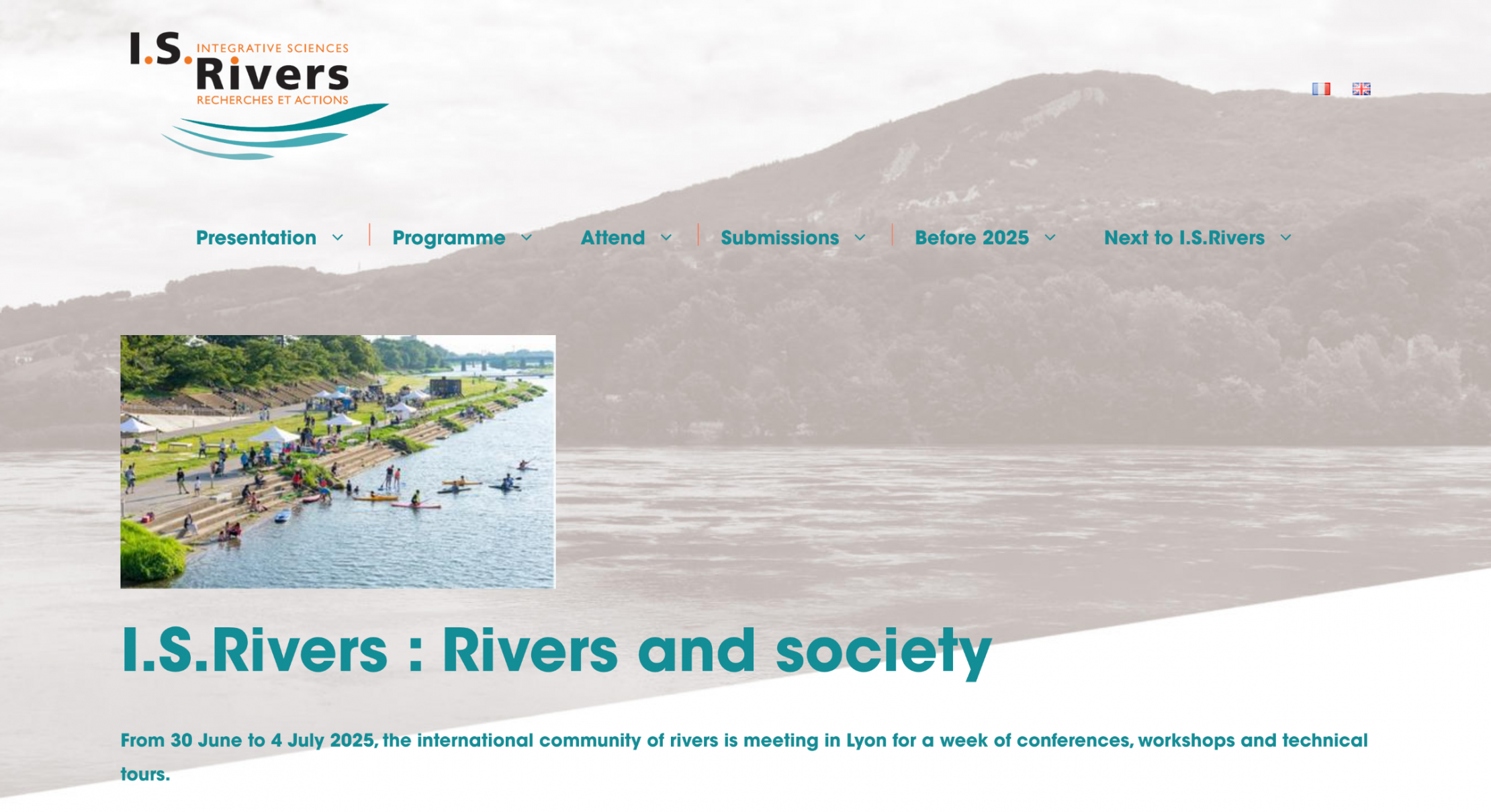
I.S.Riversの公式HPより転載
https://www.assograie.org/isrivers/en/2025/06/02/i-s-rivers-is-in-a-month/
私は「都市河川の機能と価値」というセッションで、乙川リバーフロント地区の整備から活用、そしてONE RIVERの発足に至るプロセスと、その過程に伴う意識変化に関して発表をおこないました。都市の川を単なる水辺空間として活用するのではなく、流域でつながる自然の一部として捉え、それを活かしたまちづくりを進めようとする世界最先端の取り組みを、熱意いっぱいに伝えてきたつもりです。
お次は、東京で開催されたInternational Socio-Hydrology Conference(国際社会水文会議)です。Socio-Hydrology(社会水文学)とは、2010年代に勃興した新しい学術分野であり、2021年にオランダで1回目の会議が実施され、今回の東京開催が2回目という、こちらも新たな取り組みです。メインテーマは「社会水文学の拡大と主流化そして学際的な実践の展開」ということで、単なる学術研究を超えた、現場での実践アプローチについても議論をすることが目指されました。
私は “Transdisciplinary waters” (学術を超えた水)というセッションで、アンケート調査を中心にONE RIVER 流域研究室のこれまでの取り組みについて発表をしました。どのようにして、自然や地域社会に対する人々の「つながりの意識」が育まれるのか、これまでの研究を通じた暫定的な仮説を紹介することができました。この学会における最後の発表(大トリ)で、お疲れモードの中ではありましたが、発表スライドが多くの方に写真を撮られていたので多分思いは通じたのだと思います。
嬉しいことに、2回とも発表後に多くの研究者から前向きなコメントをいただくことができました。それらを振り返ると、ONE RIVERの活動を支えている川の自然に対する感謝やリスペクト、「乙川愛」とでもいうべき感情がどのようにして育まれているのか、という点がもっとも興味を惹いたようでした。
それは、特にヨーロッパ圏の研究者による(鼻息荒めの)リアクションから明らかでした。例えば、フランスで川の再生を研究されている先生からは、ドイツ・ミュンヘンの事例を出して、「市民の川に対するプライドや感謝がなければどんな川の再生もうまくいかない」と応援をいただきました。さらに都市計画を専門とするスペイン人の先生からは、「川の多様な価値を体験し、川と結びつき、それが人々のアクションを起動するというプロセスは世界共通であり、 “一体何が人々のスイッチを押すのか” を研究することが大事だ」というコメントもありました。
「愛」などというと、研究っぽくない印象を持つ方も多いと思います。確かに、愛のような自然に湧き出る感情は、科学的に説明できる(説明していい)現象ではありません。しかし、川の再生(River restoration)や持続可能性科学(Sustainability science)の分野などでは、この「説明できない衝動」を重視する学術的な動きが起き始めているのもまた事実なのです。小さな島国の小さな川、乙川で生じている人々の活動は、やはり世界の先端を行く現象なのだと、強く確信しました。
その上で面白かったのは、私の発表の質問で、必ずといって良いほど「日本文化の影響はないのか?」と聞かれた点です。言い換えれば、「日本流」のアプローチに興味を持ち、そこから学ぼうという姿勢の研究者が多いように思いました。
確かに、海外(特に欧米)と日本では、同じ「Rivers(川)」という言葉が指す概念のイメージや社会的な意味は大きく異なります。まず、欧米では日本と比べて一つの流域(集水域)が大きいという特徴があります。例えば、日本の1.5倍ほどあるフランスの国土はたった6つの主要河川流域で区分されており(画像参照)、100を超える数の一級水系が指定されている日本と大きく異なります。結果として、山に降った雨が海に出るまで時間がかかるため、川の水量は日本に比べてかなり安定しています。つまり、洪水(水害)というのはあまり一般的な社会問題ではありません。
また、欧米では、川は今でも国際的な舟運路として利用されており、単なる水資源を超えた重要な経済資源でもあるのです。その上で、雨の量が少なく(例えばフランスの年間平均降雨量は900 mm程度で、日本の半分くらいです)、森林面積も小さい(同じくフランスの森林率は30%程度で、日本の半分以下です)ため、渇水(水不足、Water Scarcity)が深刻な問題になりやすい傾向があります。渇水になると、水道水が止まるだけでなく、農業の生産性が低下し、さらに物流を担う船の航行もできなくなり、経済的な大ダメージが生じます。
つまり、欧米人にとって川とはまず第一に恵みなのです。それは、単に経済的なものとしてだけではありません。洪水が起きづらい性質上、欧米の川は(一般論として)堤防などの構造物が少ないこともあり、都市に近い水辺空間として活用される傾向にあります。豊かな水辺の体験も、彼らにとって重要な川の恵みに他なりません。
これは、この数年、毎年のように国土のどこかで大きな水害が起きている日本人の感覚とは大きく違うのではないでしょうか。「暴れ川」という呼称や、「八岐大蛇伝説」などの洪水伝承から考えても、やはり、私たちにとって川から最初に想起されるのは恵みというよりもリスクなのだと思います。
では、日本人はこれまで川を避けてきたのかと言えば、当然そうではありません。川はリスクであると同時に、生活に必要な恵みの存在でもある。その両面性の中で私たちの祖先は複雑な文化を育んできたに違いない、私はそう考えています。例えば、各地でみられる「水神社」や、川を舞台にした多くの花火大会などは、その一つではないでしょうか。リスクもありながら、私たちの生活に欠かせない川の恵みへの感謝(愛)を、次世代に受け継ぐ技術が、我が国には溢れています。
今回、国際的な研究発表を通じて得られたのは、これらの新たな研究の視点でした。これからも、「川への愛」を育み、継承していくための地道なプロセスを探究していきながら、都市の暮らしと自然をつなぐ「日本流」のアプローチとして世界に発信していきたいと考えております。みなさまご協力をよろしくお願いいたします。























